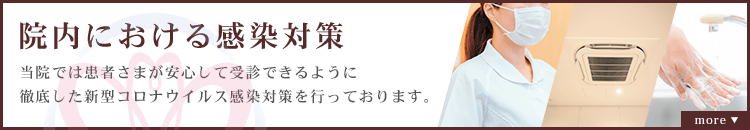睡眠時無呼吸症候群とは
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apneas Syndrome:SAS)は睡眠中に呼吸が浅くなるあるいは呼吸が止まってしまう病気です。呼吸が止まりますため、そのたびに脳で覚醒反応が起こり、睡眠の質が低下します。そのため昼間の症状として日中に眠くなる、注意散漫になる、疲れがとれないなどの症状が出現します。一方、就寝中は何度も中途覚醒し、何度もトレイに行くことになります。また睡眠時無呼吸症候群は肥満、高血圧、糖尿病のような生活習慣病と密接に関りがあり、重篤な場合は心筋梗塞や脳血管障害のような生命に関わる疾患を引き起こす可能性があります。
こんな症状の方はご相談ください。
- 「大きないびきをかく、または繰り返しいびきをかく」と指摘されたことがある
- 「寝ているときに呼吸が止まっている」と指摘されたことがある
- 息苦しくて目が覚めるときがある
- 太っている、もしくは1年以内に体重が3kg以上増えた
- 夜中に何度もトイレに起きる
- いくら眠っても疲れが取れない、熟睡感がない
- 朝起きた時に口や喉が渇いている
- 集中力や記憶力が低下してきた
- 居眠りによって事故を起こしそうになったことがある
上記にいくつか当てはまる症状がある方は、自宅での簡易睡眠検査をお勧めします。
睡眠時無呼吸症候群の定義
日中過眠もしくは、閉塞型無呼吸に起因する様々な症候(日中の倦怠感、集中力の低下、強度のいびきなど)のいくつか伴い、かつ無呼吸低呼吸指数(AHI)≧5とします。
AHI (Apnea Hypopnea Index:無呼吸低呼吸指数):睡眠1時間当たりの無呼吸低呼吸の回数
- 軽症:5≦AHI<15
- 中等度:15≦AHI<30
- 重症:AHI≧30
睡眠時無呼吸症候群の検査
① 簡易睡眠検査
呼吸や血中の酸素の状態を測定し、睡眠呼吸障害の程度(AHI)を求めます。検査は自宅で行うことが可能で、AHIが40以上で眠気などの睡眠時無呼吸症候群の症状が明らかな場合は、持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)の対象になります。AHIが40未満でしたら、さらに精密検査(PSG検査)が必要になり、専門の病院やクリニックで行います。簡易睡眠検査はCPAP療法後の治療効果判定の検査として行うこともできます。
② 終夜睡眠ポリグラフ検査 (Polysomnography:PSG)
睡眠障害の原因と程度が正確に判断できる検査です。専門の病院やクリニックに検査入院し、診断を行います。体に様々なセンサーを取り付け、睡眠の状態(眠りの深さや分断の状態)、呼吸状態、心電図等の評価をします。当院にてPSG検査による精密検査が必要と判断されました患者様は、専門病院もしくはクリニックへご紹介させて頂きます。
睡眠時無呼吸症候群の治療
① 持続陽圧呼吸(CPAP)療法
CPAP療法は、睡眠時に鼻にマスクを装着し一定の空気圧を送り込み、上気道の閉塞を取り除き、気道を確保する治療法です。CPAP装置からホース・マスクを介して、処方された空気圧を気道へ送り、常に圧力をかけて空気の通り道が塞がれないようにします。SASに対し、現在最も治療奏功率の高い治療法(CPAPを使用した患者様の95%でAHIを5以下に改善)といえます。
② マウスピースによる治療
マウスピースとは、下あごを前方に固定して空気の通り道を開くようにするものです。マウスピースの作成は、健康保険の適用になります。医師の判断にてマウスピースによる治療が適当と判断された場合、歯科医院でマウスピースを作製して頂くことになります。マウスピースは体への負担が少なく手軽に行える治療ですが、CPAP程の治療効果が得られないなどの欠点もあります。マウスピースが奏功しやすい方の特徴として、SASが重症でない、肥満がない、顎が小さい、側臥位睡眠で無呼吸が少ない事などが挙げられます。
③ 外科的治療
気道閉塞の原因がアデノイド肥大や扁桃肥大などであった場合には、手術で摘出することにより構造を変化させ、症状の改善が期待できます。また、鼻閉を起こす鼻疾患は、CPAPや口腔内装置の治療を妨げるので、手術が必要となることがあります。手術効果の高い方の特徴としては、SASが重症でない、肥満がない、扁桃腺が大きいなどが挙げられます。
④ 生活習慣の改善
減量
減量により皮下脂肪の量が下がると、気道が拡張し、SASの改善が期待できます。体重の変動とAHIの変化について観察した研究によると、平均して10%の体重減少でAHIが30%減少し、20%の体重減少でAHIが50%減少したという報告もあります。
体位変換
仰臥位では、舌根沈下により上気道が狭小化するため、側臥位により上気道の狭小化を起こりにくくする。ただし重症のOSASでは、側臥位就寝の効果は低いとされています。
アルコール/睡眠薬
アルコールや睡眠薬は、上気道の筋肉群の活動性を弱めるため、睡眠時に上気道の狭小化をもたらします。就寝前の飲酒や睡眠薬の服薬はなるべく避けることが望ましいです。
喫煙
喫煙は血液中の酸素の濃度が低下させることや、咽喉頭部の炎症を起こすことがあります。鼻やのどの粘膜が慢性的な炎症を起こし、上気道が狭小化してしまうことがあるので、禁煙が望ましいと考えられています。